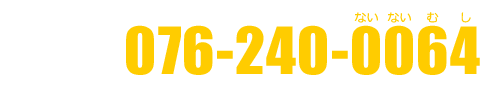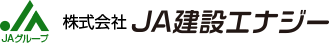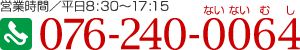害獣の種類
ドブネズミ

尾がやや短めの、大型のネズミ。褐色がかった灰色をしていることが多い。クマネズミとは違って高い場所への移動は苦手としているため、床下や川辺、地下街などで生活している。食性もクマネズミとは逆で肉や魚介類を好んで食べる習性があり、生きた小動物をすばやく捕食するために発達した筋肉を持っている。哺乳類ではヒトに次いで最も増加した種であり、南極以外ほぼすべての大陸に生息している。

クマネズミ

尾が長い中型のネズミ。名前の通りクマのような体色をしており、背面は褐色・茶褐色であり腹部は白っぽい。配管や電線の上り下りなど高所への移動が得意であり、天井裏を騒々しく駆け回る。壁伝いに黒ずんだ毛皮の跡が見られたときはクマネズミの通り道である可能性が高い。警戒心が強く捕獲しづらいうえに、近年では殺鼠剤に耐性を持つものが現れており増加の一因となっている。なんでも食べるが大半は雑穀であり、肉や魚を食べることは少ない。

ハツカネズミ

身のこなしの軽い小型のネズミ。体色は白色、灰色、褐色、黒色など個体によって様々。家の中であれば家具の隙間、外であれば他の動物が掘った巣穴などを巣とする。雑食性であり穀物・植物を好み、農村の家屋など自然環境に隣接した建物で見られることが多いため、家畜飼料やペットフード、農作物に被害を出す。実験用・愛玩用に改良されたものは「マウス」と呼ばれる。

ハクビシン

ジャコウネコ科の動物であり、額から鼻にかけて特徴的な白い線があるのがその名の由来となっている。夜行性であり木や外壁を登ることができ、繁殖力も高い。頭が通る程度の小さな隙間でも侵入でき、甘い果実や野菜を好んで食べるうえ、同じルートを辿って毎晩やって来るため、果樹園だけでなくトマトやウリ類のビニールハウスなどにも深刻な被害を出す。また、屋根裏に住み着いて騒音や糞尿による住宅被害を出すこともある。

ハト

街中でも日常的に見られる、ずんぐりとした体型が特徴の鳥。特徴的な首を振って歩く姿は、「歩行の安定性を高めるため」とも「視覚情報を安定させるため」とも言われている。方角を知る能力に加えて帰巣本能もあり、かつては通信用の伝書鳩として活躍した。数多くの神話や伝説などに登場し、群れを成す性質から平和の象徴とされていることでも有名。一方で、都市部を中心に食害や糞害の多発、餌付け行為によるトラブルなどが問題となっている。

その他、アライグマやテン、イタチ、タヌキなどの防除も承っております。

石川県内のシロアリに関するご質問・ご相談にお応えいたします。
お気軽にご利用ください。